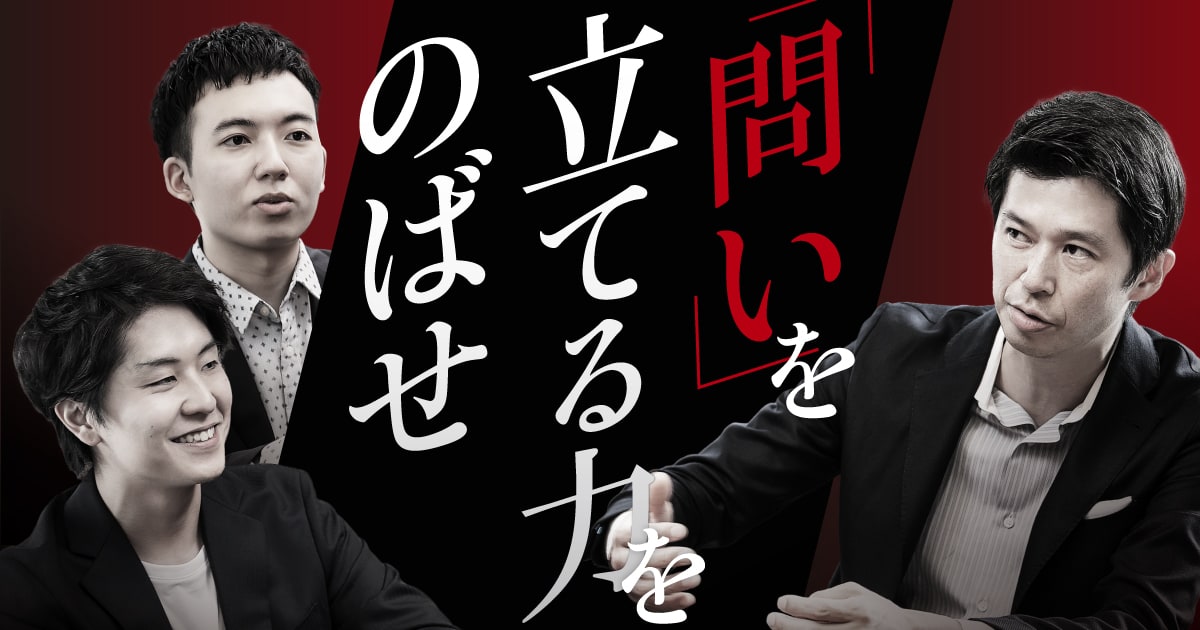INTERVIEW
ダイナミックかつクリエイティブに業界を変える。個性豊かな事業家の卵たちの挑戦

Goodfindが注目する企業で活躍する社員の、就活や現在の仕事を深掘りする「Goodfindが行く!OBOG訪問」。今回はSpeee内定者の島口敦光さんと、新卒4年目でマネージャーを担う辻淳基さん、10年目で2つの事業の事業責任者を務める上野健人さんの3人に、就活や現在の仕事についてインタビュー。三者三様の経験から見えてきたのは、事業開発の奥深さでした。
【謝礼あり】読後アンケートご協力のお願い(計6問・所要時間1〜2分)
SPONSORED BY 株式会社Speee
話し手

上野 健人
株式会社Speee デジタルトランスフォーメーション事業本部
リフォームDX事業部長 兼 ウェルネス事業部長

辻 淳基
株式会社Speee デジタルトランスフォーメーション事業本部
不動産DX2事業部 マネージャー

島口 敦光
京都大学文学部 人文学科4年
株式会社Speee 内定者
SECTION 1/5
それは全リソースを投下してでも、やりたい仕事か?
⸺Speee内定者の島口さん、新卒4年目でマネージャーを務める辻さん、10年目で複数の事業責任者を務める上野さんの3人に、それぞれの就活や入社後の経験を伺っていきます。まずは辻さんの学生時代や就活について教えてください。
辻:体育会サッカー部でレギュラーとしてプレーしながらセカンドチームのキャプテンも務め、どう組織を強くするかに日々思考を巡らせていました。
就活は最初は何も考えずコンサルや総合商社、国家公務員などを見ていました。その中で「全リソースを投下すればこうした会社の内定は得られそうだけど、そこまでして行きたいのか?」と、ふと立ち止まって。まずは自分がやりたいことを言語化しようと、自己分析や情報収集を行いました。

そこで気づいたのは私自身、「自分が何か大きなものを変革した」という事実を作りたいと思っていることでした。何かを変えてきた人の中でも、業界や社会といった大きなスケールで変革を成し遂げてきた事業家に魅力を感じ、将来の目標を「突き抜けた事業家」に定めました。
⸺突き抜けた事業家になるためにSpeeeを選んだのはなぜでしたか?
辻:一つは、新しい市場を切り拓いている会社だからです。私は事業家には「課題を捉える力」が必要だと考え、その難易度が最も高いセールスからキャリアをスタートしようと思っていました。その中で、Speeeではテクノロジーを活かしてまだ世の中にない変革を生んでいるという事業特性上、潜在的な課題を捉える力が身につくのではと考えたのです。
もう一つの理由は、事業成長に組織成長が追いついていないことです。様々な会社の新卒2〜3年目の社員に業務内容を細かく聞く中で、Speeeの若手は裁量や機会の量が圧倒的でした。その要因は組織として仕組化が整っていない中で事業が立ち上がり続けていることにあるとわかり、その組織・仕組みづくりにまで若手のうちから携われる可能性が高いことに、自分が「突き抜けた事業家」になる勝ち筋を見出しました。最短距離で「突き抜けた事業家」になるためには、あと1年修士を続けるよりも、1年でも早くSpeeeに飛び込んだほうが良いと考え、大学院を中退しました。
⸺入社後は新規事業セールスを担い、全社表彰式で新人賞を受賞されたとか。活躍の秘訣と、仕事で感じているやりがいを教えてください。
辻:新人賞をもらった一番大きな要因は、ただ決められた役割としての営業を行うのではなく、自分が事業全体の成長にいかにインパクトを与えられるかを考えながら行動していたことにあると思います。その甲斐あって、2年目からチームリーダー、3年目からは営業組織のマネージャーを任されました。

2年目は4人を、3年目では30人弱をマネジメントする中で、チーム全体で試行錯誤し、自分一人では起こせなかった大きな変化を生み出せる点にやりがいを感じています。大きな変化を生み出すためには、自分がそれまで「定数」だと思っていたものを「変数」として捉え直す必要があり、意思決定の難易度が高まる分、面白さも増しています。
SECTION 2/5
哲学者、いざビジネスの世界へ
⸺次にSpeee内定者の島口さんにお話を伺います。島口さんはどんな学生生活を送ってきたのでしょうか?
島口:大学では哲学に打ち込んできました。1回生の頃から哲学の本を読み漁り、3回生で卒論はほぼ書き終えて、4回生では修論を考えるような学生生活です。哲学研究会というサークルの副会長として、研究発表会や、一般の人に哲学を知ってもらうイベントの企画・運営もしていました。
⸺そこまで哲学に打ち込んできた中で、研究の道に進む選択肢はなかったのですか?
島口:その選択肢も持っていて「将来は博士号を取って教授も目指せるだろう」とすら思っていました。一方で、哲学者として社会の人々にとって重要な役割を果たすためには、大学に閉じこもっているだけではダメだと感じたのです。だからこそ、一度仕事を通して社会を見てみようと就活を始めました。

⸺就活ではどんな企業を見ていて、Speeeに内定承諾した決め手は何でしたか?
島口:最初はコンサルを中心に見ていました。経営者を相手に仕事をする機会が多いため、社会の構造を支える人たちがどんな価値観を持っているのかがわかるのではと考えたからです。しかし、あるファームのインターンに参加した際、社員や周りの学生の雰囲気や考えが自分とは合わなさそうだと感じました。
対してSpeeeのサマーインターンでは、一緒に働きたいと思うメンターに出会うことができました。フィードバックの鋭さや丁寧さはもちろんですが、目の前の仕事を楽しみながらも、今後のキャリアや事業・社会を長期的な視点で捉えている姿が印象的でした。
入社の決め手もやはり「人」で、代表の大塚さんと話した経験が大きかったです。私は大塚さんも広い意味では哲学者だと思っているのですが、社会や人間がこの先どうなっていくのか、自分たちの人生よりも長い時間軸で捉え、事業という形で社会に還元している姿が、私が理想とする将来像の一つだと感じました。
⸺現在どのようなキャリアビジョンを描いていますか?
島口:就活時点では「3年程働いて研究の世界に戻ろう」と思っていましたが、今は企業内哲学者やCPO(Chief Philosophy Officer)と呼ばれる、会社のミッションを戦略に落とし込んだり、社員の思考力向上を推進したりする役割に就くことを視野に入れています。哲学者として企業で働く道を実現することで、ある意味「哲学」という業界を変革していきたいと思っているのです。
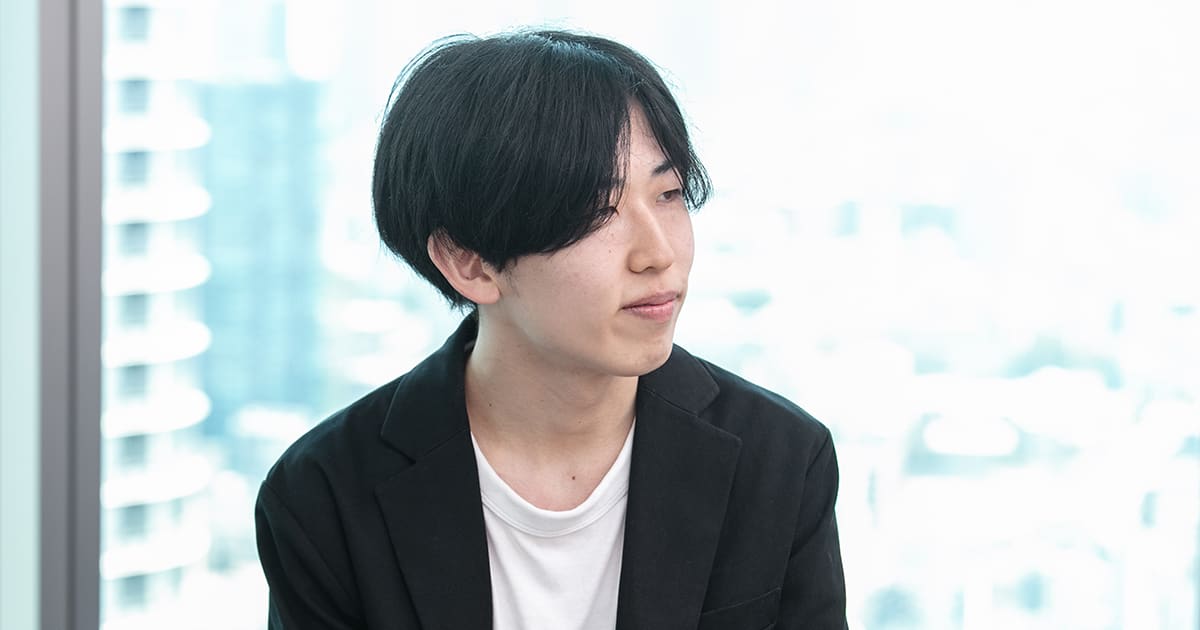
そのためにも20〜30代前半はビジネスへの理解を深めようと考えています。入社後はマーケターを担う予定ですが、上司からは「自分で市場を見つけて事業を大きくしてほしい」と言われていて。Speeeでは初期配属時の職種名に捉われることなく、事業家になるために必要なことは何でもできると聞いています。その環境を存分に活かして営業活動なども経験し、一人前の事業家として責任者も担っていきたいです。
SECTION 3/5
業界トップ事業の責任者だから見られる景色
⸺上野さんはどんな学生で、どう就活を進めていたましたか?
上野:辻さんや島口さんとは反対に、一つのことに打ち込むというよりも、色々な経験をすることに重きを置いていました。学生団体AIESEC(アイセック)の活動をしながら、サークル活動や、新聞の飛び込み営業のアルバイトをしたり。4回生の時には就活支援サービスの会社で長期インターンをしながら、理系学生向けの就活支援をする学生団体も立ち上げました。
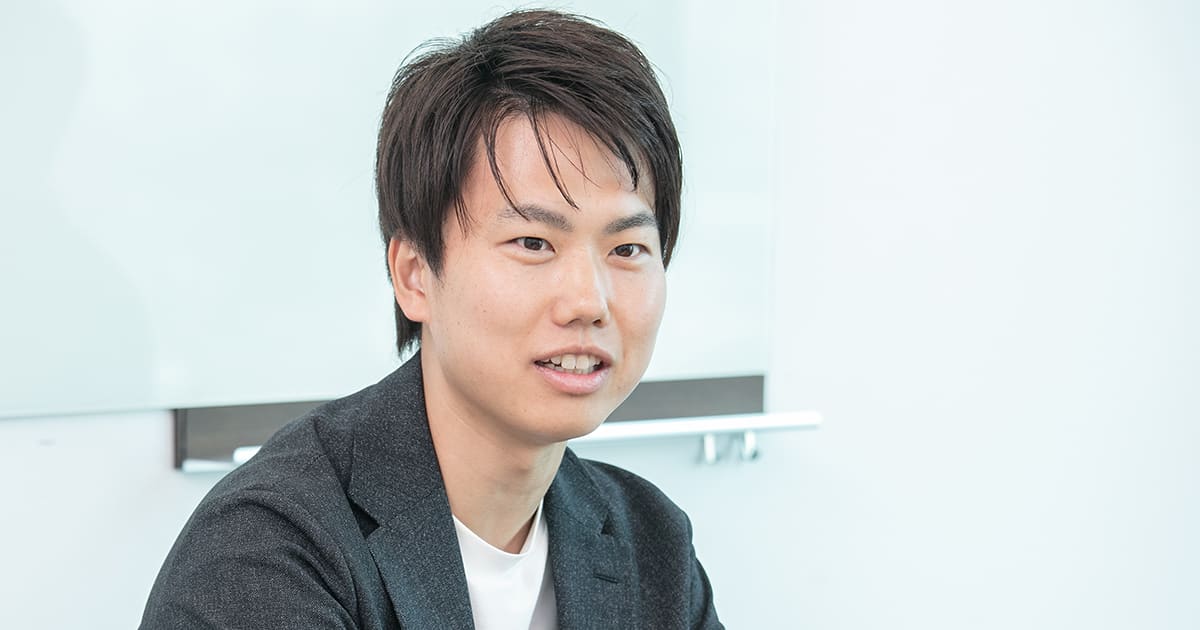
就活では、都市計画や環境エネルギー計画を行う大企業のサマーインターンに研究職として参加し、そこで「自分には研究職は合わない」と理解しました。何か大きな構造の変革に関わりたいと思っていた私にとって、業務内容は希望に合っていた一方で、そこでは数十年間、仕事内容が変わらない人がいるように変化を感じにくい環境だとわかったのです。
そうした経験を基に、就活の軸を「テクノロジー × 変化が激しい環境 × 中長期的に産業変革に携われること」に定めました。ただ、当時はITといえばスマホゲームかデジタルマーケティングの企業がほとんどで、軸に合う会社を見つけるのが難しく。Speeeは私が探した中で唯一、テクノロジーで事業をつくっていくというケイパビリティを持ちながら、経営陣が産業変革まで見据えている会社で、社風にもマッチしたことから入社を決めました。
⸺新卒1~2年目はマーケターを務めた後、営業企画や事業企画、経営企画を担われてきたとのことですね。
上野:1年目の配属先は立ち上げフェーズの不動産領域DX事業でしたが、マーケ担当者が自分と事業責任者を合わせて3人しかいませんでした。どこから手をつけて良いのかわからないくらいタスクが山積みだったので、とにかく先輩の仕事を奪いながら自分のものにしていきました。
Speeeでは現時点でできることをするという「積み上げ思考」ではなく、最初からあるべきゴールを定め、その達成に向けた過程を計画する「逆算思考」で事業をつくっているため、やるべきことや一人ひとりの機会が増えやすい構造です。リクルートの創業者・江副浩正氏の「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という言葉の通りに、機会を与えられるほど、自分自身はいつの間にか成長していて、事業が伸び、また機会が増える。私自身もその循環の恩恵に預かってきたと思います。
⸺新卒3年目から事業責任者を担う中で感じる面白さとはどんなものですか?
上野:Speeeの事業責任者は、事業を「経営」している感覚になれるのが面白いところです。事業のビジネスモデルやターゲットの選定、採用やM&Aなどの手段も含めて、すべて事業責任者に一任されています。

そこからもう一段階、面白さのフェーズが上がったのは、サービスが業界トップになった時です。業界トップの事業をさらに成長させるためには、他社を模倣して課題を見つけ、それを解決するだけでは不十分です。課題、つまり理想と現実とのギャップを「見つける」のではなく「自らつくる」ことが必要となります。どれだけ高い場所を理想とし、どんな業界を形作るのかが、私の意思決定に委ねられることになるのです。そうした「あるべき」から考えて課題をつくり、業界を変える挑戦はダイナミックかつクリエイティブで、これは事業開発でしか味わえない面白さなのではないでしょうか。
SECTION 4/5
事業開発に必要な「情理のバランス」とは
⸺世代も、想いも、経験も異なる皆さんが考える「Speeeの事業開発の魅力」とは何ですか?
島口:事業開発における情理のバランスの良さが魅力だと思います。先日大塚さんと、これからの時代、人間の定義が変わってくるのではないかという話をしました。昔から、人間は理性的思考ができる唯一の生き物であると言われてきましたが、AIの登場がこれを覆しつつあります。AIでも思考することができるようになった世の中で、人間の価値は、感情や意思、共感、想像といったものの方に、より重きが置かれるようになるのではないかということです。
Speeeの社員はこの、情理の「情」の部分も大切にしている人が多いと感じています。高い論理的思考力を駆使しながら事業や産業を変革しようとしている原動力には、目の前で困っているユーザーやクライアントへの共感があると考えており、当社に根付くこの価値観が広がっていくと、人間というものがもっと面白くなるだろうと思っているのです。

上野:論理的思考力に関しては、社内でも「あるに越したことはないが、あるからといって良い事業家になれるとは限らない」と言われています。では良い事業家になるために必要な要素は何かというと、人間としての器の大きさです。クライアントやユーザーの役に立ちたい、大きな構造変革を成し遂げたいという想いと、やりきる胆力。それがなければ「逆回転してしまう」、つまり自分がやりたくないことをやらない理由を作り出すために論理的思考力を使うようになってしまうのです。
ただ“賢い人”が活躍できるとは限らないのが、事業開発が「ビジネスの総合格闘技」と言われる所以の一つであり、だからこそSpeeeでは顧客志向や産業変革への想いを重視しています。
辻:論理的思考力を正しく駆動させるためには、やはり意思決定の量と質が必要で、これは私や上野さんの経験からも想像してもらえるでしょう。別の視点でSpeeeの事業開発の魅力を挙げるとすれば、本気で業界・社会を変えに行けるフェーズの事業がたくさんあることです。
上野さんが責任者を務める事業もそうですが、当社の多くの事業が業界に深く入り込んでいるがゆえに、高いシェアを獲得し、多様化するニーズに連鎖的に応えられる段階に入っています。事業の1→10を行う中で、様々な0→1が生まれ続けているようなイメージです。そのため機会も無限に増え続けていますし、事業だけでなく業界・社会の変革にまで携われるという面白さがあります。私たちのように事業家になりたい、事業開発に没頭してみたいと思う方にとって、最高の環境がSpeeeにはあると思います。

SECTION 5/5
後輩におすすめしたい一冊
上野:事業の課題を構造的に捉えて成功まで導く、Speeeで日々行っている事業開発そのものを学べる一冊。
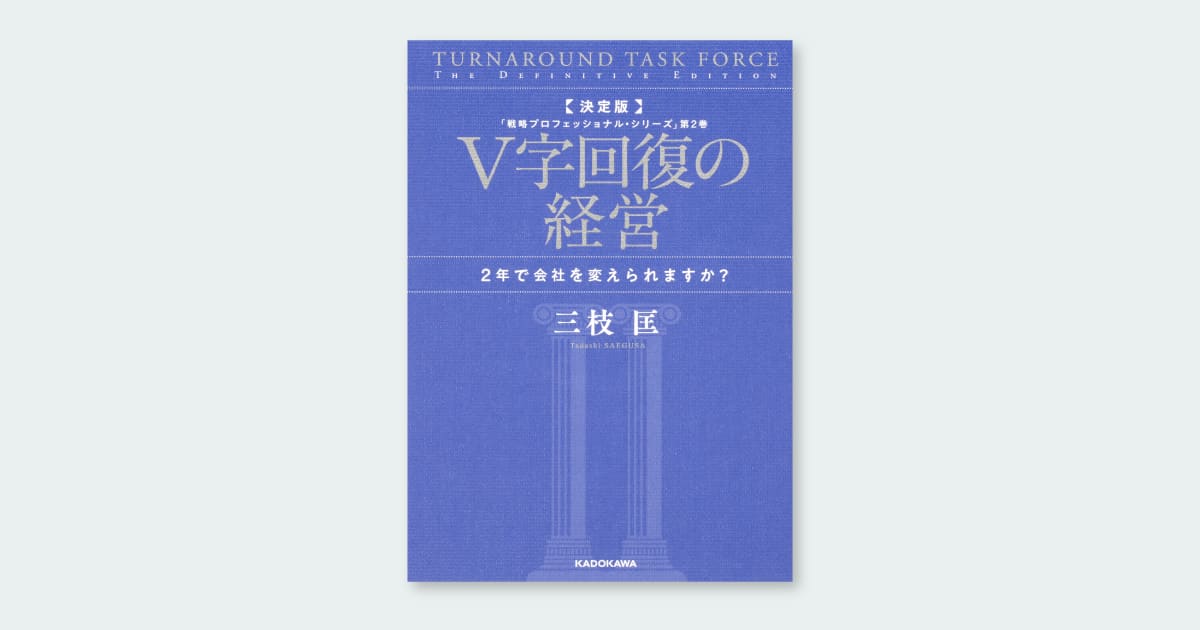
辻:就活時に事業家とは何か、突き抜けた事業家になるためには何が必要かを言語化するのに役に立った一冊。
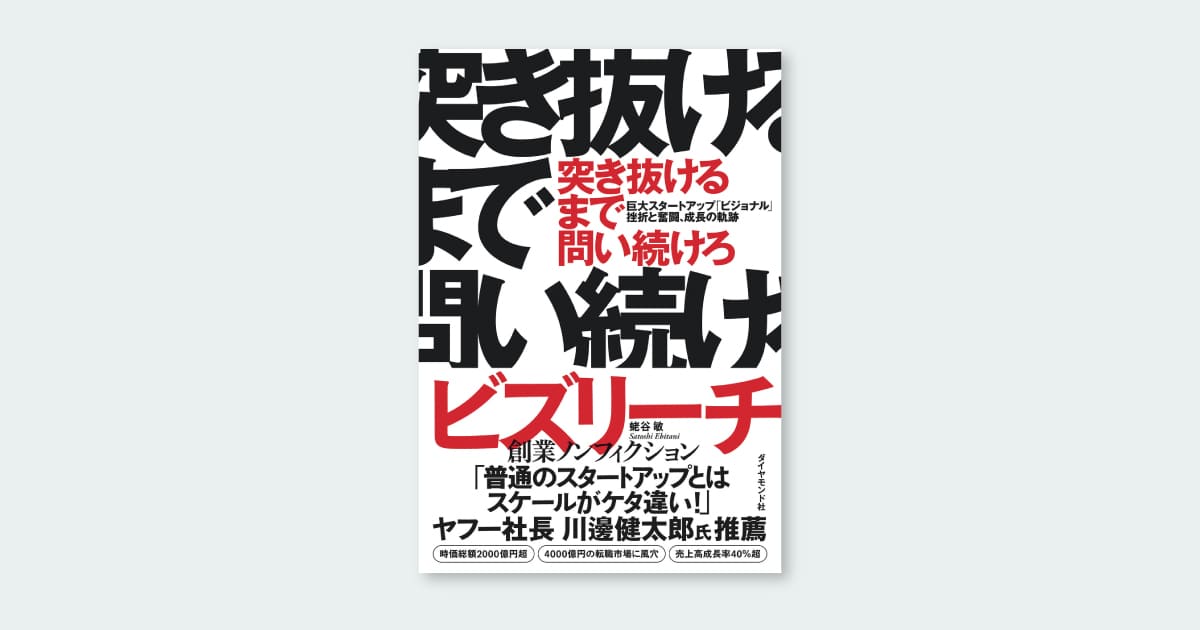
島口:「ケア」とは異なる価値観を理解し尊重すること。哲学書だが事業家としても大事な要素を学べる一冊。
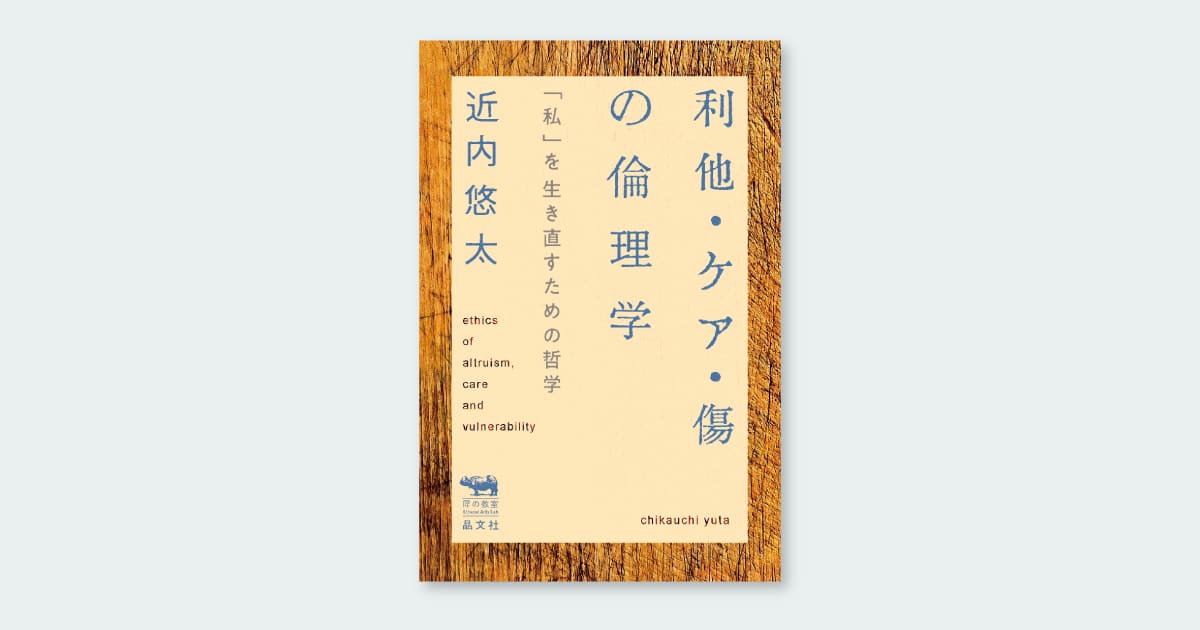
Speeeのエントリーはこちら
〈27卒説明選考会〉【事業開発に挑戦】事業創造で日本のDXを牽引するBizDev集団~ワーク解説付きグループディスカッション選考会
記事の感想をお寄せいただいたGoodfind会員の中から抽選でAmazonギフト券をプレゼント!(計6問・所要時間1〜2分)
編集: